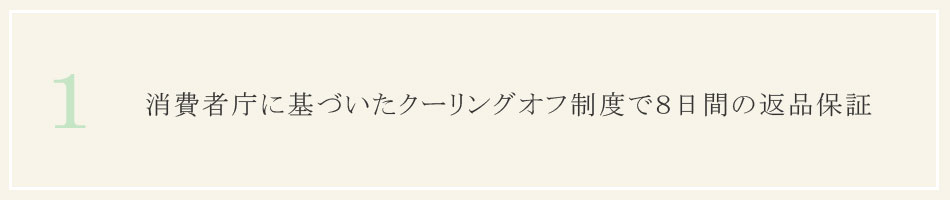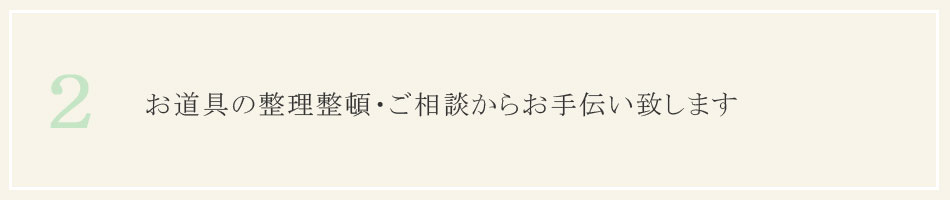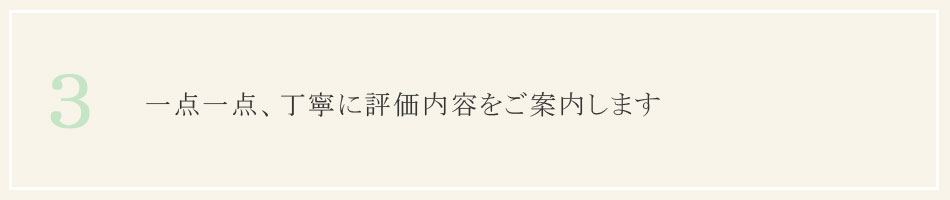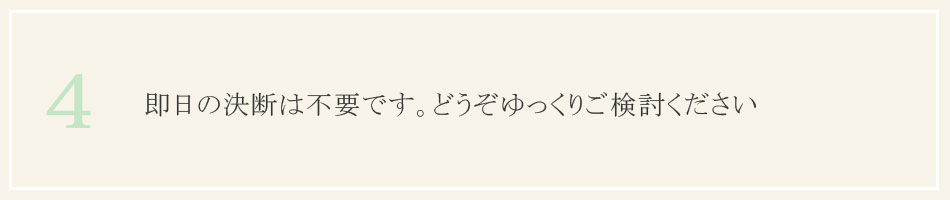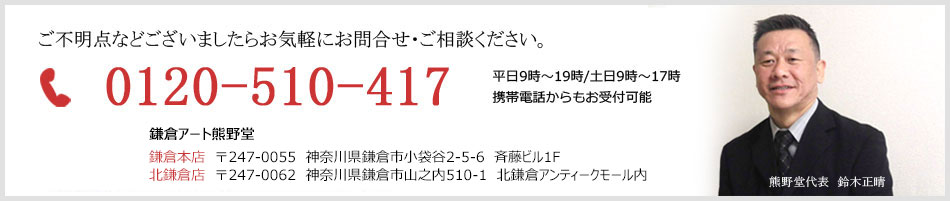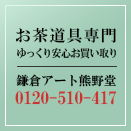大阪も、茶道・茶道具との縁が国内で最も深い地域の一つです。
堺市は茶の湯を発展させた町といわれ、茶の湯の天下三宗匠の一人、千利休の生誕地でもあります。
利休以外の天下三宗匠である今井宗久・津田宗及が活躍したのも堺でした。
そんな大阪でしたが明治維新・文明開化のあと、茶の湯を支えてきた大名や武士がいなくなってしまい、一時的に茶の湯は衰退してしまいます。
ですが、跡見花蹊によって初めて女子教育に茶の湯が取り入れられるなど、茶の湯復興への動きがいち早く生まれたのもこの大阪でした。
今では女性が茶道を当たり前に嗜んでいますが、明治が初めてなんて驚きですよね。
阪急創業者の小林一三のコレクションを収蔵する逸翁美術館や、曜変天目茶碗を含む国宝を多数収蔵する藤田美術館。
京都の藪内(やぶのうち)流と通じる茶室をもつ旧西尾家住宅など、大阪には茶道との強い繋がりが感じられる名所も多く存在します。
利休が大成させた武者小路千家の茶道を現代まで約200年間、継承・伝播してきた木津家の本拠地ももちろん大阪にあります。