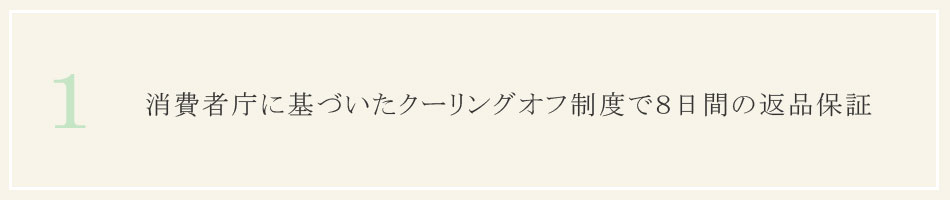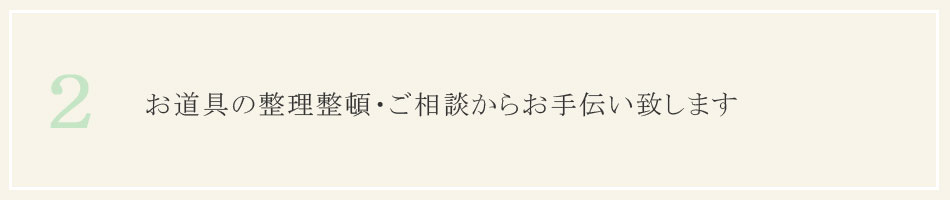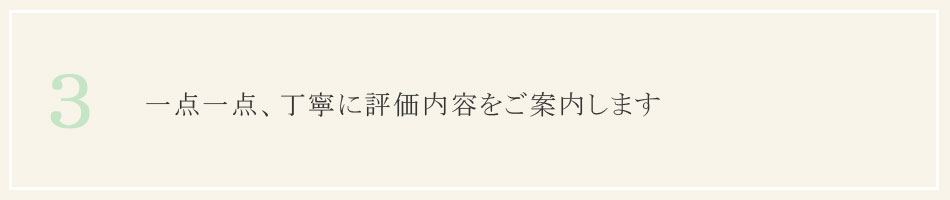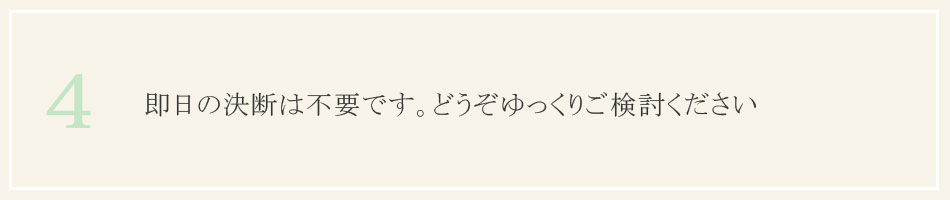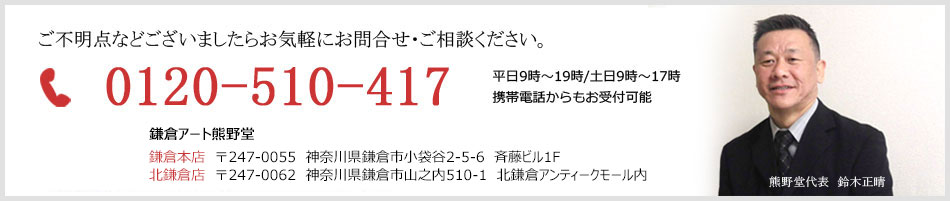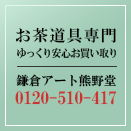京都はそのイメージ通り、昔から茶道・茶道具は関わりが非常に強い場所です。
「大徳寺」はあの一休さんがいた寺院で、お茶と禅を結びつけたといわれています。
わび茶の開祖といわれる村田珠光、そして千利休、さらには古田重然(号は織部)、小堀政一(号は遠州)といった大茶人がこぞって参禅した寺院として有名です。
日本最古の茶園といわれる高山寺「栂尾(とがのお)茶園」は、日本で初めて茶が作られた場所であるといわれ、栄西禅師が中国から茶壺と茶の実3粒を持ち帰り植えたのが始まりとされています。
日本三大茶の一つ宇治茶も、高山寺の手助けによって発祥したと言われています。
京都は茶道の各流派の家元(本部)が多い地域で、全国に3室ある国宝指定の茶室のうち、『待庵(たいあん)』と『蜜庵(みったん)』の2室が京都にあります。
茶道具も多く焼かれており「京焼」「清水焼」「楽焼」が有名で、清水卯一・近藤悠三といった陶芸家の人間国宝も排出し、ほかにも楠部彌弌(やいち)など、有名陶芸家が多い地域でもあります。